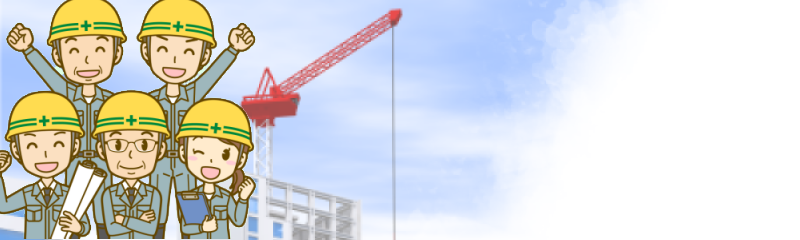
建設キャリアアップシステム登録
お知らせ
2024/04/06
5/1~5/5まで、GW休暇を取らせていただきます。
最近の更新
YouTubeチャンネル(ずんだ書士)
建設業許可は必要?
メリットとデメリット
経営事項審査の審査項目の
仕組みについて
建設キャリアアップシステム
の使い方
当事務所の特徴  (あえてデメリット)
(あえてデメリット)
- 平日は週一しか空きがありません。
- 建設業に関する事務作業に普段携わっているため、平日は週一と土日祝しか空きがありません。
お急ぎの業務には対応できかねますので、ご了承ください。
- お問い合わせは、メールフォームでお願いします。
- 電話をかけて頂いても、直ぐに対応できないためメールフォームからお願いいたします。
営業電話防止のため、直通の電話番号は掲載しておりません。